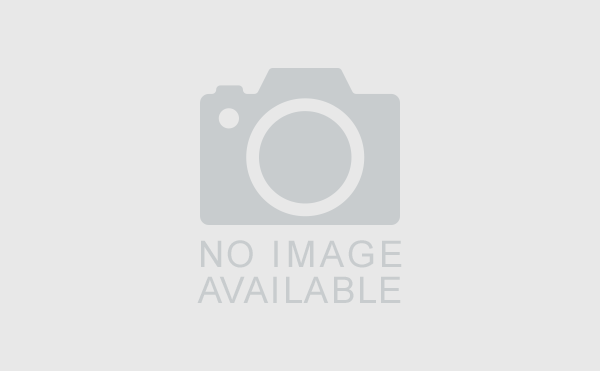CODE Letter 28号&プロジェクトニュースの発行
いつも、皆様よりご支援をいただき、誠にありがとうございます。
CODE Letter 28号とプロジェクトニュースを発行致しましたので、ご覧くさい。http://www.code-jp.org/letter/index.htm
尚、ご希望があれば、可能な限り直接みなさまのところに出かけてプロジェクトのご報告を申し上げますので、ご遠慮なく事務局まで申しつけて下さい。
CODE Letter 28号
・「支える事は支えられる事」 CODE理事・財務部会長 村上忠考
・フィリピン・レイテ島地滑り災害について
・震災を語り継ぐ「留学生セミナー」開催
プロジェクトニュース
・スリランカ津波復興支援
・アメリカ南部ハリケーン・カトリーナ支援
・イラン北東部地震支援
・イラン・ザラント地震支援
・その他のプロジェクト
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
CODE海外災害援助市民センター