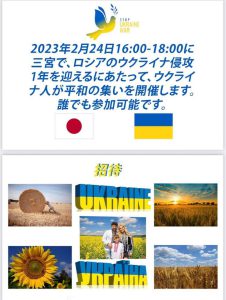学生インターンの島村優希です。
前回に引き続き、MOTTAINAIやさい便をお届けしているSさんご一家へのインタビュー内容をお伝えします。
********************************
「ウクライナがほしいのは平和だけ。でも負けることではない。勝利による平和。」
Sさんには、三人の娘と一人の息子がいて、長女はボーイフレンドと共にウクライナに残っています。故郷に残っている娘さんはマスクを提供するボランティアをされています。私が娘さんとどのように連絡を取っているか伺うと、
「もちろん毎日電話している。彼女は大丈夫って言うんだけど….日本でもアラートは見れて、彼女がシェルターに入っているか確認できるから、チェックしている。ウクライナは今団結している。お互いを助け合うから、私たちの軍隊は強くて勇敢だ。後ろで支えるボランティアの存在が本当に重要。」と仰っていて、故郷に残る娘を強く心配をすると共に、彼女が国のために活動をしていることへの誇りが感じられました。また、お話を伺った際で既にクレメンチュークの気温は1度以下であるのに、娘さんが電力不足で冷蔵庫さえ使えない状況にある、と心配した表情で伝えて下さいました。
Sさん一家が日本に来られてからは、言語の違いや手続きなどで困惑したことが多々あったみたいですが、兵庫県の多くの支援団体や人々から支援を受けることができたそうです。Sさんは日本に対して、「私達が言いたいことは、『本当に日本に感謝している』ということ。多くのサポートや何でも受け入れてくれて、感謝している。また、数日前にウクライナのために戦って亡くなった日本人の兵士にも感謝している。彼は命という一番大きなものを差し出した。私はこれに本当に感謝している、他の多くの外国兵を含めて。」と仰っていました。
また、MOTTAINAI野菜便に関連して料理の話をしている際に、Sさんは故郷の家を思い出し、「私たちはここも愛せる家にしようとしている、ここにも家が必要だから。私は毎日を生きたい。」と伝えられました。
最後に、戦争に対してのSさんとVさん(Sさん母)の思いです。
Sさん「ウクライナがほしいのは平和だけ。でも負けることではない。勝利による平和。」
Vさん「子供たちは平和な場所で生活しなければいけない。ウクライナに勝利を。」
ウクライナ東部の奪還が進んだ地域もある一方で、お話にあったように、ウクライナの気温が益々下がる中、電力不足の未だ厳しい状況は刻々と続いています。ご家族や友人の多くがウクライナに残る避難民の方は、日本での新たな生活をやりくりしながら、遠く離れた故郷に残った大切な人々の心配をして、日本からできる支援をされています。では私達一人一人ができることは何なのでしょうか。この記事を読んで、もう一度しっかりと考えてみて頂けると幸いです。
********************************
MOTTAINAIやさい便へのご協力お願いいたします。
MOTTAINAIやさい便では、新鮮な野菜をお届けする中で見えてきた問題やニーズに対してもサポートしています。
自転車の提供、通訳、引っ越し、傾聴などのボランティアに学生さんなどにかかわってもらっています。
ご寄付は、野菜の購入だけでなく、運送代やボランティアの方の交通費などにも活用させていただいています。ぜひご協力お願いいたします。
 Sさんと娘さん
Sさんと娘さん